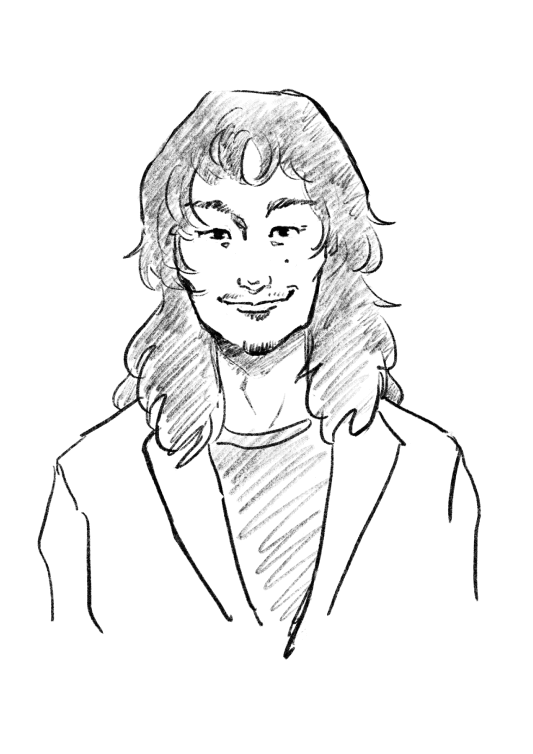困る人がいてほしい”
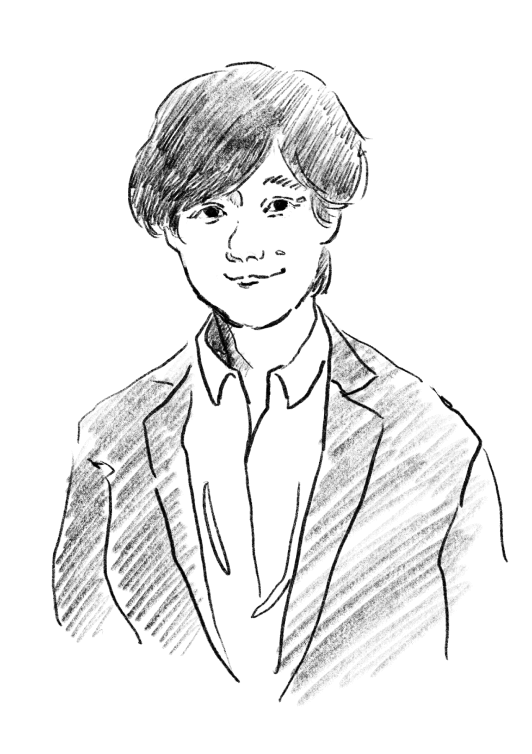
株式会社WORDS代表取締役。経営者の顧問編集者。ダイヤモンド社等を経て2018年に独立。『メモの魔力』前田裕二著、『福岡市を経営する』高島宗一郎著、『佐藤可士和の打ち合わせ』佐藤可士和著など書籍の編集・執筆。SNS時代の「伝わる文章」の探求をしています。著書に『書くのがしんどい』(PHP研究所)。ポテトサラダが好き。
ぼくが「自由に好きな本をつくれる最高の出版社」を辞めた理由
- #ブランディング
- #生きがい
- #社長
- #編集者
ほんとうは雑誌編集者になりたかった
学生時代のぼくは、大人になって、ご多分にもれず満員電車に乗って、ふつうに会社員になるのが嫌でした。あと、小さいころから、おもしろい話を聞いてそれを人に伝えるのが好きで。オリジナルの新聞をつくって親戚に配り歩いたりしていたんです。だから「将来は新聞記者もいいなあ」なんて思っていました。
ところがよくよく調べていくと、ジャーナリズムってけっこう大変そう。ときには戦場にも行かなきゃいけないらしい。「それはやだな」と思ってやめました。それで「おもしろい話を聞きたいなら、べつに新聞記者じゃなくてもいいよな。むしろ、雑誌の記者のほうが向いてるかも」と思っていました。
で、大学3年ぐらいのころに『ポパイの時代』という本を読んたんです。そこには、雑誌『POPEYE』編集部の、びっくりするぐらいカオスな様子が書いてありました。ある人は「いま西海岸ではスケボーが流行ってるんだ」といってスケートボードで会社に来たり、大学生がめちゃくちゃ遊びにきていたり、常に誰かのおすすめの音楽がかかっていたり……。
「え、こんな世界があるんだ」と思いました。
好きなことをやって、それが仕事になるってめちゃくちゃいいなあ。楽しそう。それで就活はマガジンハウスを第一志望にしました。
でも蓋を開けたら、当時マガジンハウスは求人すらしてなかった。ほかの出版社も軒並み落ちて、唯一受かったのが「日本実業出版社」でした。ビジネス書や実用書に強い、老舗の中堅出版社です。
ルノアールでサボる日々
最初の配属は営業でした。ビジネス書の書店営業。雑誌の編集者になりたかったぼくからすると、やりたいこととはぜんぜん違います。それでも自分なりに楽しもうと思って、できる範囲のことはやっていました。
最初の半年くらいは言われた通り、ルートを回ってました。1日5、6件、与えられたエリアを回る。一応それはちゃんとやって。「書店のフェアやるから、フェアの注文取ってこい」とかもちゃんとやって。
でも、だんだん飽きてきちゃったんです。
営業部の唯一の同期に、ホソノくんって人がいました。A型で、藤沢出身で、わりとまじめなんだけどちょっと天然っぽい、愛されキャラの人でした。たぶんぼくより根はまじめなんだけど、ちょっとちゃらんぽらんに見える感じ。
ぼくは一見おとなしそうに見えて、ぜんぜん従順じゃない、タチの悪いタイプです。ぼくはホソノくんを「ちょっとルノアール行きましょうよ」とそそのかして、一緒にサボっていました。
で、アイスコーヒーを飲みながら「架空日報」を書くんです。その日の日報を先に書いちゃうんですね。本当は行ってないのに、その日に回るであろう書店の名前と「店長不在、担当者不在」なんて書いて。
ぼくはそのあともデニーズに行ったりしたいんですけど、ホソノくんは根がまじめなので「いや、さすがにちょっと、俺は書店いくわ」と、先に行っちゃって。ぼくは一人で「つじ田」のつけ麺を食べてから「しょうがないなあ、そろそろ行くか」なんて。いま考えるとダメすぎますね。
はやく編集者になりたくて
2年目ぐらいからは、ちょっと自分なりにがんばるようになりました。とにかく、少しでも編集っぽいことがやりたかった。それで、おすすめの新刊をまとめた「ビジネス書通信」を作って、書店さんに配ったりしていました。新聞をつくるのは、半分趣味みたいなものだったし。
あと、カタログみたいなものもつくっていました。「新刊でこういうのが出ます」というのを、文章だけだとつまんないなと思って、カバー画像つきで紹介してたんです。A5の半分ぐらいの小さいファイルにして。それが好評だったのかどうかは、正直わからないんですけどね。
「編集者」というものへのあこがれ
当時のぼくは「編集者」というものへのあこがれがすごくあったんです。会社の飲み会で編集者に話しかけて「すごいあこがれてるんです。打ち合わせとか見せてもらえませんか」と言って、ついて行ったりして。
「そば屋で打ち合わせするけど、くる?」といわれて、緊張しながら池袋のそば屋にいきました。そこで編集者と著者が、赤字を入れたゲラを眺めて「ここなんですけどね」とかやっているんです。ぼくは「すげー、本物の著者と、本物の編集者だ」「これがゲラというものか」なんて思いながら見ていました。すっごいウブな青年ですよね。
そのとき見せてもらったのは「図解 サーバーのしくみ」みたいな本でした。正直、いまだったら「つまんない本だな」って思う気がします(笑)。でもそのときは、本を書く人なんてもう「先生」だし、編集者はそんなすごい人とやりあっている、めっちゃすごい人。そんなイメージだったんです。
売れない本はダメだ
入社3年目になっても、まだ編集部に行けませんでした。それなのに2年目の後輩が、ぼくより先に編集部に異動になったんです。それで、もう我慢できなくなっちゃって。「どこでもいいから、とにかく編集がやりたい」と思って転職活動をしました。
で、たまたま受かったのが「中経出版(現KADOKAWA)」という出版社です。「きみ、営業部なのに勝手に新聞なんてつくってるの? おもしろいね」といって採用してくれました。
やっと念願の編集者になれました。でも意外と「自分の好きな本」を思いっきりつくれたわけではありません。
若いときはサブカル系の本や、佐藤可士和さんみたいなクリエイター系の本がやりたかったです。でも企画を出してみても、あんまり通りませんでした。「売れない本はダメだ」といわれてしまう。
ぼくも「そうだよな」と納得していました。営業部のときから「編集者が好き勝手につくった、独りよがりな本は売れない」「どの棚に置かれるか計算するのが大事だ」と、さんざん叩きこまれていたからです。
そうやって「売れる本をつくらなきゃ」という考えが、自然と体にしみついていきました。
売れるっておもしろい!
中経出版では、編集の師匠に出会いました。飯沼さんという編集者です。いまでも覚えているできごとがあります。著者の人からもらってきた原稿が、言葉を選ばずにいえば「くそつまんなかった」ことがあるんです。
ぼくは「え、飯沼さん、これぜんぜんおもしろくないです」「どうするんですか」と言いました。飯沼さんは「まあ、うん、わかってる」「ちょっと待って」と言って、パソコンでカタカタとやりはじめました。
それから1、2週間ぐらいして、飯沼さんから原稿が送られてきました。すると、最初とはまったく別物の、ものすごくおもしろい原稿に変貌していたんです(笑)。もう、ゴリゴリにリライトしてて。
しかもそれが、最終的に50万部も売れたんです。
ぼくは衝撃を受けました。それまで、編集者の仕事は、著者が書いた原稿にフィードバックしながら、うまく本にしていくことだと思っていました。でも飯沼さんは「これ、もはや飯沼さんが書いてますやん」というぐらい手を入れていたんです。
もちろん著者によってもやりかたは変わってきますし、なにが正しいというわけではありません。ただ、その本がすっごく売れたのは事実です。ぼくはそれを目の当たりにして「売れるって、おもしろいな」と思いました。
これがぼくの編集の原体験です。「文章は読まれなければ意味がない」というポリシーは、いまだに大切にしています。
悲しきベストセラー
その後、中経出版から星海社、ダイヤモンド社と、けっこう順調に転職していったと思います。ありがたいことに、何冊かベストセラーも出すことができました。
ただ、ぼくの担当したベストセラーって、どれもちょっと悲しい思い出があるんです。
はじめてのベストセラーは『たった1分で人生が変わる片づけの習慣』という本でした。当時は「片づけ」がテーマのビジネス書はあまり例がなくて、タイトル会議でも「片づけで売れるの?」といわれたのを覚えてます。それでもがんばって押し通して、ちゃんと売れたので、すごくうれしかったです。
ところがその翌年に、こんまりさんの『人生がときめく片づけの魔法』が出て、世界中で売れてミリオンセラーになるんです。正直、すっごく悔しかったですね。
その後、ダイヤモンド社では『アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の言葉』がベストセラーになりました。ただこれも、おなじ「アドラー心理学」のテーマでミリオンセラーになった『嫌われる勇気』には敵いませんでした。
だから「100万部売ってるすごい編集者」に対してのコンプレックスはあるかもしれないです。「編集者であるからには、ミリオンを出さなきゃ」という思いはずっとあります。それだけは、いまだに達成できてないですね。
いま「顧問編集者」という仕事をはじめて、やっと自分の居場所ができた気がするんです。やっと1番になれたというか。負けず嫌いなんですよね。なにかで認められたいのかな、たぶん。
つらかったダイヤモンド社時代
ダイヤモンド社は、自由に好きな本をつくりたい編集者にとって、天国みたいな会社だと思います。「年間で何冊つくらなきゃいけない」という発行点数のノルマがなくて、1冊1冊にちゃんと時間をかけられます。
そんな恵まれた環境にいるのに、ぼくはなぜか、すごくつらかったんです。
本の売れ行きを見る指標で「紀伊國屋パブライン」というのがあります。専用のウェブサイトにコードを入れると、自社の出してる本の売れ行きが、多い順にバーッとならぶ。それを見ると、自社の編集者のなかでの自分の立ち位置がなんとなくわかるんです。
中経出版のときは、出すとたいてい上位に食い込んでいました。だけどダイヤモンド社では、滑っちゃうともう、1ページ目にも出てこない。すごい売れたと思っても、上には上がいる。1日に10冊売れていたらまあまあいいのですが、ダイヤモンド社くらいになると30冊、40冊売れているものもふつうにあって。
ずっと悔しかったですね。負けず嫌い。
ちょっと売れる本を作っても、数か月後にはもう、べつの売れる本がでてくるんです。ずっと売り伸ばしてもらえるわけじゃない。中経出版で「片づけ」の本が当たったときは、半年ぐらい新聞広告も出してもらっていました。でもダイヤモンド社では、どんどんおもしろい新刊が出てくるんです。
会社の規模は中経出版が100人いないぐらいで、ダイヤは300人ぐらい。規模が圧倒的にちがうわけでもなかったのですが、できる人ばっかり集まっていたんですよね。
吉井和哉の「Winner」を聴いて泣く
べつに比べたくなんかないのに、どうしても比べてしまう。「新聞広告に誰の本が並ぶか」とか。そういうのも毎回気にしては「くそー」と思っていました。吉井和哉さんの「Winner」を聴いて、公園で泣いていたんです。
「走れ、止まらずにこらえるんだWinner」「初めから僕らなにもなかった」って。
「超いい歌……」と思って(笑)。同僚に話したら、笑われたんですけど。人よりも負けず嫌いなんでしょうね。「順位とかじゃないんだ。好きな本がつくれたら、それで幸せなんだ」とは思えなかった。「売れないとダメだ」と思ってしまっていました。
やりたいことなんて意外となかった
「編集者」という肩書き自体にあこがれてたころに比べたら、ずいぶん変わりましたよね。スレちゃったのかな(笑)。
『ポパイの時代』を読んでいたときは「遊ぶように働いて、それでお金がもらえるなら、そんないいことはないな」と本気で思っていました。
ダイヤモンド社では、実際にその夢が叶いました。企画は出し放題だし、基本的に落とされない。「なんでもいいよ」みたいな感じなんです。エロと反社会的なもの以外なら、自分の好きな本がつくれる。漫画でもなんでもOKです。
でも、そう言われちゃうと案外、やりたいことなんてないんですよね。
なにか夢中になれるものも、改めて考えるとないんです。そんなにオタク気質でもないし。「遊ぶように暮らす」とか「好きなことで起業する」って、たしかにあこがれます。でも、じゃあ自分にそれほどの個性や、オタク的に好きなものがあるかって聞かれたら、ないんですよね。
受験勉強をしている最中は「これが終わったら絶対に遊びまくろう」と思うじゃないですか。「受験まではめちゃくちゃ勉強するけど、そのあとは夢の大学生活だ。旅行しまくって遊びまくって、好きなことをやるんだ!」って。
でも案外、飽きるんですよね。大学1年生の半ばぐらいで。好きなことをやるのに飽きてしまう。
夏休みの宿題をやっているあいだは「これがなかったら、いっぱい遊びにいけるのに」と思うクセに、いざ宿題が終わっても、べつにどこにも行かないんです。
ただ縛られていた反動で「自由がほしい」と思っていただけ。実際に「はい、どうぞ自由にしてください」と言われると、案外なんにもすることがなかったんですよ。
好きなことやって「……で?」
「好きなことで生きていきたい」と思って編集者になった。でも実際やってみたら、なんか「……で?」ってなったんです。好きな人に会いに行きました、本を作りました、まあまあ売れました「……で?」って。 けっきょく、好きなことをやるんじゃ続かない。飽きちゃうんですよね。
でも顧問編集者をはじめてから、その虚しさがなくなったんです。喜んでくれる人がいて、それによって売上が上がったり下がったり、採用が増えたり減ったりする。
「人の役に立ってる」感覚って、もしかしたら自分のために必要なのかもしれないです。
もちろん本だって、読者がいるんだから、誰かの役には立っています。でも、生活必需品ではない。言ってしまえば「おせっかい」な商品だなとも思うんです。
2011年に震災が起きました。
ぼくも東京にいたからけっこう揺れて、はじめて「死ぬかもしれない」と思いました。テレビをつけたら、東北ではもっと大変なことになっていて。でも、しばらくするとぼくはまた、東京で本を作っているんです。
ふと「自分のやっていることは、誰の役にも立っていないんじゃないか?」という気がしました。「本当に緊急事態になったとき、本なんて、トイレでお尻を拭くぐらいにしか使えないじゃないか」と。
そのあと転職もして忙しくなって、その虚無感はしばらく忘れていました。でも、心の奥底にはずっと「無駄なものを作っているんじゃないか」という意識はあって。で、ダイヤモンド社に入って4、5年目ぐらいで、限界がきたんですよね。
自分が死んだら困る人がいてほしい
中経出版のときは所帯も小さかったし、自分が会社に貢献している感覚がありました。当時は「お前が活躍しないと、会社は潰れるぞ」と言われていたんです。
「来月、お前がその本を作んないと、うちの会社は潰れるから。なんとか出してくれ」と。実際のところは、そんなにやばい会社ではなかったと思うんですけどね。
「自分ががんばらなきゃダメなんだ」と思えたので、すごくやりがいもあったし、楽しかったんです。……楽しかったのかな。忙しかったし、つらかったけど。「絶対辞めてやる」って言いながら、内心では楽しんでいたんですよね。「こんなとこ、絶対辞めてやるー!(ニコニコ)」みたいな。
ダイヤモンド社に行ったら、点数ノルマはなくて、半期に1冊、3万部ぐらい売れる本を作れば、あとはなにをしても自由です。「来月出せなくても、いつでもいいから、よきタイミングで出して」みたいな感じです。
最初は「こんな天国ってないや」と思いました。でも、ふと虚しくなったんです。「自分が仕事しなくても、なんなら1冊も本を出さなくても、この会社は回っていくんだ」と。
自分がいまここで死んでも、この会社はなんの変わりもなく動くし、誰も困らない。
「お前の代わりはいくらでもいるんだ」「お前よりもできるやつはいっぱいいるから、べつにいいよ」――そう言われているような気がしました。
ブラック企業で有給もとれずに働いている人からすれば、すごく贅沢な悩みかもしれません。でも、ぼくにはそれが、悪魔の言葉みたいな感じがしました。「いつでもいい、本を出さなくてもいい……ってことは、ぼくはべつにいなくてもいいのか」と。自分はさほど価値がない、替えがきく存在なのだと。
ぼくはたぶん、自分が死んだら困る人がいてほしいのだと思います。
これってなんなのでしょうね。もう、ただのエゴですよね。嘘でもいいからそう言ってほしい。「君がいないと、うちの会社やばいんだから。みんな困るよ」って。実際のところは、ぼくが辞めたらまた別の人がくるだけなんですけど。でも、そう思わせてくれる環境って、すごく大事だなと思います。
働く意味を言語化する
ぼくはいま「顧問編集者」という仕事をしています。経営者の隣で、彼らの言葉を編集して、多くの人に伝える仕事です。
この仕事も、言ってしまえばべつになくてもいいんです。社長がSNSをしていなかろうが、ビジョンやミッションがなかろうが、衣食住さえあれば人は生きていけます。
でも、人のメンタルを安定させるのは、たぶん「意味」なんだと思うんです。
意味がないと、迷子になります。ぼくがそうでした。一生安泰だったんです、ダイヤモンド社にいたら。正社員だし、衣食住は保証されている。変な部署に飛ばされることはあるかもしれないけど、死ぬことはない。でも、そのときは心が死んでいました。それは、生きる意味が失われていたからです。
自分がなぜここにいるのか、わからなくなった。それこそ、ダイヤモンド社に顧問編集者がついて「君たちのつくった本が、日本を動かすんだ。いなきゃ困る職業なんだよ」なんて言われていたら「じゃあ、がんばろうかな」と思えたかもしれません。
顧問編集者はそれをやる仕事。なんか、つながりましたね。
最近「パーパス経営」が話題になりました。「役に立つ」よりも「意味がある」に価値がある時代がきている、なんて言われています。
顧問編集者がやっているのはそういうことです。「ただ社長のSNSをやっているだけじゃん」といわれたら、たしかにそうです。でも、社長の発信を通して、会社が存在する意味とか、そこにいる社員たちが働く理由をちゃんと言語化して、定義づけしようとしているんです。
会社のビジョンや、目指す世界を言語化する。社長のnoteで発信する。それを社員が読んで「そうだな」と納得する。フォロワーも伸びて、世間から評価される。そうやって「自分たちの売っているサービスって、価値があるんだ」と思えたら、働くのも楽しくなると思うんです。
書籍編集の仕事はやりがいがない、というわけでは決してありません。いまもダイヤモンド社で、いきいきと働いている人はたくさんいます。そういう人はたぶん、自分で仕事の意味を見つけて、使命感をもってやれているのだと思います。ぼくもそれができていたら、もっと楽しく働けていたかもしれません。
でもぼくは、そこがちょっと弱かったんです。「それは誰かが決めてよ」と思ってしまって。もともと「おもしろい話を聞いて、みんなに伝えるのが好き」というのが、最初のモチベーションでしたから。
いま、顧問編集者のお客さん先の会社にも、かつてのぼくみたいな人がいるかもしれません。そういう人が社長の発信を見て、自分がそこにいる意味を感じてくれて、いきいきと働けるようになったら、いちばんいいなあと思いますね。