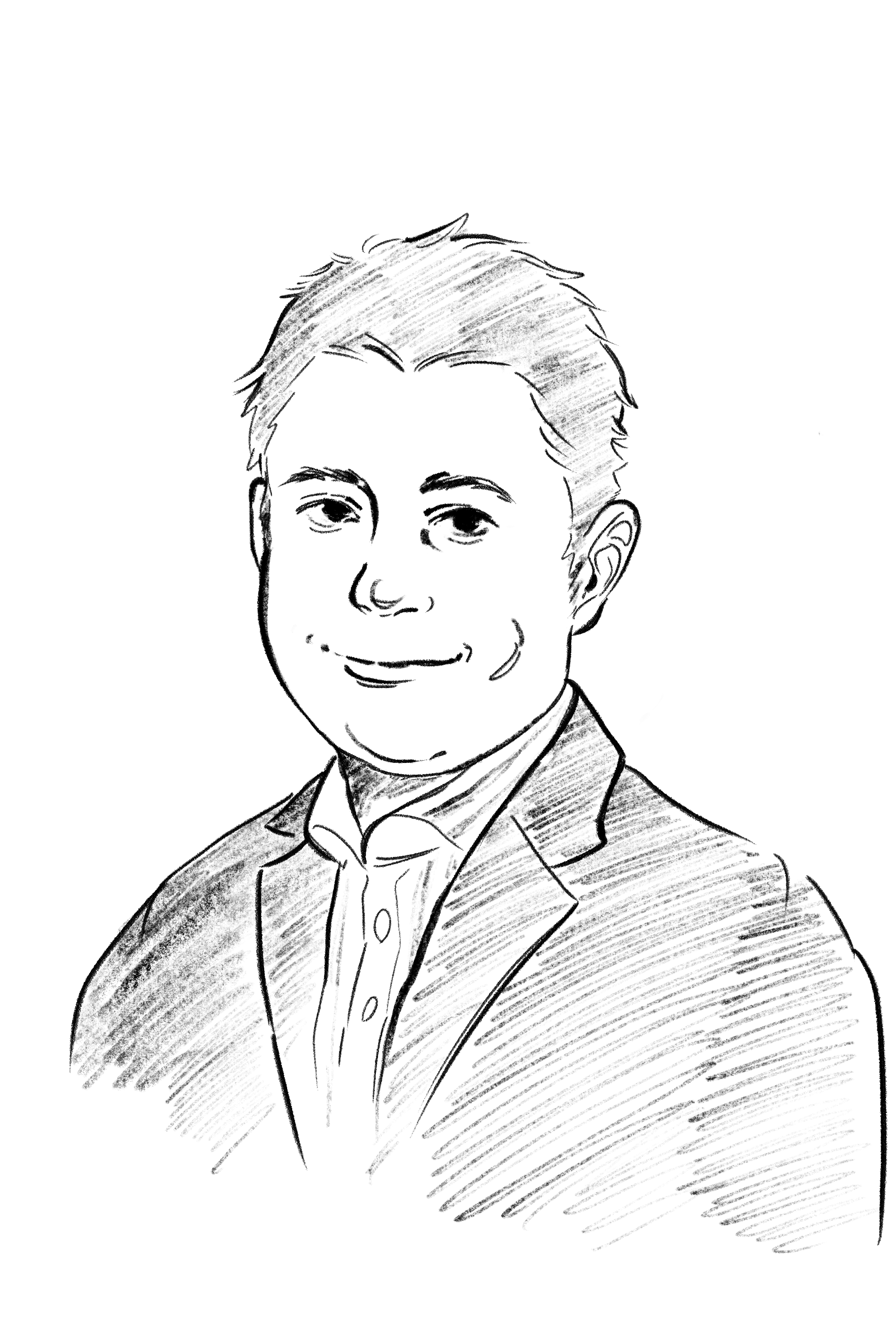ゼリーを食べたんです”
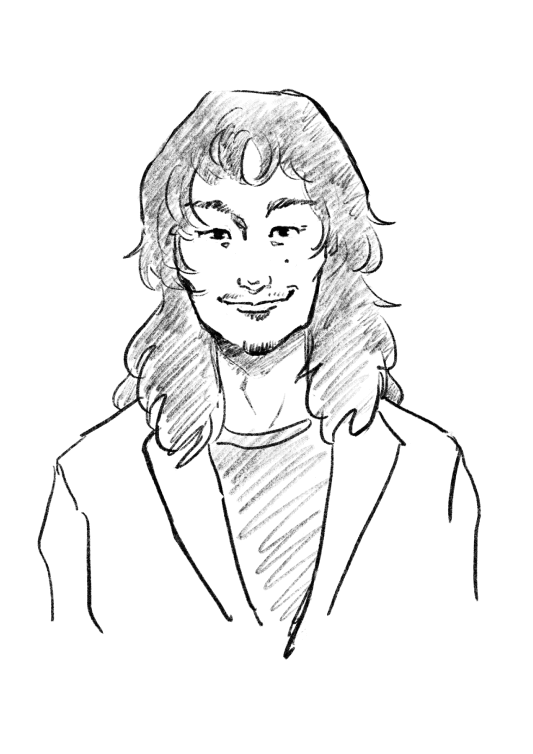
弁才天代表取締役。1988年、名古屋市生まれ。明治大学卒。広告会社などを経て独立。その後、古着屋や立ち飲み屋などを経て、2019年に「覚王山フルーツ大福弁才天」を出店。フルーツ大福人気の火付け役となった。現在は「のれん分け」という形でフランチャイズ展開も行っており、全国70店舗を展開する。
なんの取り柄もなかったぼくが、年商数十億円の大福屋の社長になったいま思うこと
- #ブランディング
- #生きがい
- #社長
「オール3」の小学生だった
ぼくは名古屋市でいちばん人数の多い小学校に通っていました。いろんなやつがいましてね。ガキ大将もいれば、勉強ができる秀才くんもいれば、運動神経のいいやつもいる。母数が大きいので、各ジャンルのトップがみんな強かったんです。
ぼくは別にどれにも当てはまらない、冴えないやつでした。いちばん勉強ができるわけでもないし、いちばんかっこいいわけでもないし、いちばん足が速いわけでもない。
小学校一年生の通知表は、ぜんぶ「○」でした。「◎、○、△」の3段階評価で、ぜんぶ「○」。要するにオール3です。なんの取り柄も、ダメなところもない。なんにも秀でていないし、別にそこまで悪くもない。ぜんぶマル。
ぼくはお母さんによく思われたくて、「○」の中に小さい丸を書きたして「◎」にしたんです。でも、よく見たら形がいびつなので、すぐにバレてしまって。「あんた、なにやっとるの!」と、めちゃくちゃ怒られました。
トイレで泣きながらゼリーを食べる
小学校でのぼくのあだ名は「ゼリーくん」でした。おやつのゼリーの「ゼリーくん」。小四のときの遠足で、お母さんが弁当箱にゼリーを入れていたんです。ランチタイムになると、みんなで芝生にシートを広げてお弁当を食べますよね。ぼくは友達のもりもっくんとか、ツジムーランとか、カワハラとかと食べていて。
ぼくらは「二軍」でした。「一軍」の男子たちが授業中に大きな声でわいわいはしゃいでいるときに、ぼくらは隅っこでこっそり話していて。女の子からはぜんぜん見向きもされない。でも「俺らのほうがシュールでおもしろいこと言ってるよね」みたいな、そんなグループでした。
ところが、その遠足のランチタイムだけ、女の子たちがこっちに来たんです。ぼくのゼリーを見つけて「ゼリーだ、ゼリーだ」ってはしゃぎだして。ぼくは女の子となんて喋れなかったので、無言でゼリーをすっと差し出したんです。
その日から、ぼくは「ゼリーくん」ってあだ名になりました。
でもそのときは決して、嫌だとも悲しいとも思いませんでした。存在が認められたことがうれしかったので。「ゼリーくんちょっと消しゴム貸して」「ゼリーくんちょっと鉛筆とって」みたいなコミュニケーションも増えてきて。それまでは空気みたいな存在だったのが、ちょうどゼリーみたいな、半透明ぐらいの感じになったんです。
それから少しして、今度は社会科見学がありました。
ぼくは「ゼリーくんって呼ばれてるし、当然、みんなまたゼリーをもらいにくるはずだ」と思いました。それでお母さんに「ゼリーが必要だ。それも一個や二個じゃない、大量に必要なんだ」と頼んだんです。それで、ゼリーを二袋、クラスの人数ぶん用意してもらいました。イチゴミルク味と、フルーツアソート味。ぼくは弁当とゼリーをリュックに詰めて、準備万端で社会科見学に向かいました。
でもランチの時間になっても、女の子たちは来ませんでした。
待てども待てどもぜんぜん来なくて。最終的に、ぼくはゼリーを服のなかに隠してトイレに行って、個室で泣きながらクラス全員分のゼリーを食べたんです。
ゼリーを捨てようにも捨てられませんでした。「食べ物を粗末にするな」と教わっていますから。お母さんに心配をかけちゃいけないから、ゼリーは空にして帰らなきゃいけない。でも、自分からみんなに配るほど陽気なキャラでもない。だから食べるしかなかったんです。
女の子のひとことで「モテブランディング」ができる
中学に入ると一転、ぼくはモテはじめました。
きっかけは、中学一年の終わりがけにあった国語のテスト。ぼくはたまたま、クラスでいちばんいい点数をとったんです。そうしたら女の子から「大野くんって、見た目ちょい悪な感じなのに勉強できるんだ、すごいねー」と言われて。そのときぼくは背が高かったのと、いとこにもらったお下がりのスケーターズボンを履いて、ちょい悪風の見た目だったんです。
ぼくは「それか!」と思いました。「ちょい悪な感じで、実は勉強できる」というブランディング。これがウケるんだと。
で、だんだんそういうふうになっていきました。けっこうまじめに勉強して、クラスで2、3番ぐらいの成績になって。「大野くんは髪の毛にワックスつけたり、くるぶしソックスとかにしてるけど、実は頭がよくてちゃんとしてる」みたいなブランディングが完成されていったんです。
最終的には、1年間で20人以上からラブレターをもらったり、告白されたりするぐらいになりました。
そんなある日、うちの学校で「四天王」と呼ばれている、すごくかわいい女の子の一人から、ぼくにメールがきたんです。「大野くん、〇〇ちゃんから連絡先聞きました。かっこいいと思ってました。よかったらメル友になりましょう」と。
ぼくは天にも舞い上がる思いでした。そのときちょうど塾にいたんですが、お腹が痛いってことにして、トイレにこもって携帯を連打して、メールをやり取りしました。もう「このまま死んでもいい」って思えちゃうぐらいのうれしさで。土手を自転車で駆け下りて「ワーッ」と叫びながら家に帰りました。
で、ぼくは彼女と付き合うことになったんです。
人生初のデートは夏祭りでした。当時の親友のカップルと一緒に、ダブルデートです。彼女は浴衣を着ていました。それがむちゃくちゃかわいいんです。「うわー、まじやばい、かわいすぎる」と。ぼくは顔を真っ赤にして、けっきょくその日、彼女とひとことも喋れませんでした。
そうしたら次の日「大野くんはリアルだとおもしろくない」って、ふられちゃったんですよ。
自分が悪いんですけどね。ぼくはそれで「もう女なんか信じるか」みたいになって、高校まで誰とも付き合いませんでした。根が陰キャラなんですよね。男兄弟だし、女の子とどう喋っていいかわかんなくて。それで、どんどんひねくれていったんです。
「持てる者」への怒り
中学のころから音楽が好きになって、高校ではビートルズにのめりこみました。友達とバンドを組んで、学祭では廊下まで列ができるぐらい大人気になったんです。ぼくは詰襟の学生服をジャケットに改造して、ギターケースの中に教科書を入れて学校に通っていました。
とにかく他の誰かと比べられない、唯一無二の存在になりたかった。
カートコバーンは音楽の原動力を「怒り」と「疎外感」だと言いました。ぼくも、それに近いのかもしれないです。不満、不服、いらだち、報われなさ。そういったものが核としてあって、それを力に変えている気がします。
「最初からなにかを持っている人」への悔しさが、たぶんずっとあるんです。
極端な例ですが、アラブの石油王みたいな人がいたとして、世襲で何世代にも渡って巨万の富を築き上げていたら、そこに正面から立ち向かうのはなかなか難しいわけですよね。そこまでじゃなくても、二世タレントとか、裕福な家庭の子とか、すごい美男美女とか、そういう人って生まれながらに「持てる者」なわけです。
「こいつ、なにもしてないのに自分より上に立ってやがる」と思うと、駆り立てられるものがあるのかもしれません。
なぜか不公平だ。不平等だ。なんであいつらは最初から恵まれてるんだ。あいつは体格がよくてスポーツができる。あいつは最初から頭がいい。あいつは最初からお金持ちの息子。なんなんだ。自分は違うのに。
もし、ぼくがイケメンだったり貴族の生まれだったりしたら、こんなこと考えずに楽しく暮らしていたと思います。でもぼくは容姿も家柄もふつうで、オール3の人間だったから。既得権益とか権威みたいな「自分の上にある大きな力」に対して、ずっと怒りを感じて、反抗してきたんです。
社会不適合者のレッテルを貼られる
でも、彼らに正面から立ち向かっても、まったく勝てないわけです。
20代のころのぼくは、完全に「社会不適合者」でした。思想はアナーキーで、権力を振りかざしてくる相手にはとにかくムカついてしまって。でも実力が伴わずに、空回りしていたんです。
大学で教職をとっていたのですが、教育実習ではベテランの先生に噛みついて、反省文を書かされました。社会になんて出たくなかった。「就活なんてくだらない」と思っていたけど、内心はチキンで、自分だけ取り残されるのは怖くて。それでいろいろ受けてみたんですが、ぜんぜん受からないんです。
自分は、社会に必要とされない人間なんだと思いました。
大学は明治大学で、東京に出てきていました。でも、なんだか疲れてしまって。東京にいけば何者かになれると思ったのに、ぜんぜんなれないし。けっきょく就職を機に、ぼくは名古屋に帰りました。友達の親父さんが名古屋で小さな商社をやっていて、たまたま入らせてもらえることになったんです。
ところが、ぼくはそこを1年で辞めてしまいました。
30人ぐらいの規模で、社長はよく「うちは風通しのいい会社だ」といっていました。でも実際は、みんな裏で悪口をいっていたりするわけです。なのに公の会議の場になると、誰も意見をいわない。
ぼくは思わず「これのどこが風通しのいい会社なんですか」といってしまったんです。先輩たちからは「波風を立てるな、社会人なんだから」と諭されましたが、ぜんぜん納得できなくて。
それで、社長から「おまえは社会不適合者だ」といわれたんです。
正直、図星でした。当時のぼくは、会社の「ガン」みたいな存在だったと思います。偉そうなことを言うわりに、仕事はぜんぜん楽しくなくて。よく郊外のショッピングセンターに営業車を停めて、昼寝してサボっていました。そのくせ下手に学歴はあるから、周りのことを小馬鹿にして、プライドばっかり高くって。なんの実績もないのに講釈ばかり垂れている。典型的なダメ社員です。
ぼくはなんにも言い返せず、そのまま辞めてしまったんです。
広告代理店でトップセールスに
自分は会社員として、組織で生きていくことは難しいのかもしれないと思いました。それで「カフェでもやろうかな」と思い立って。小さくてもいいから、自分の城が欲しかったんです。
いきなり始めるのは不安だったので、まずはそういう個人店のオーナーさんの話が聞ける仕事をしよう、と思いました。それで、広告代理店に転職したんです。
オーナーさんたちの話を聞くのはすごく楽しかったです。みんなそれぞれ、自分なりのポリシーをもって経営していて。ぼくは仕事というより、人としていろんな社長と仲よくなっていきました。
仲よくなった社長が、また別の社長を紹介してくれて、コミュニティみたいになっていきました。昼からみんなでバーベキュー会をしたり、オーナーの所有する船でパーティーをひらいたりして。広告の説明なんてほとんどしていなかったけれど「淳平くんがいうならいいよ」と、どんどんお客さんが増えていきました。
それで気づいたら、全国1000人もいる営業マンのなかで、トップセールスになっていたんです。
銭勘定ばかりやってても仕方ない
会社からも評価されて、給料も倍になりました。最初はうれしかったです。ようやく、社会から認められた気がしました。
でも、だんだん「このままでいいんだろうか」と思うようになったんです。
個人店のオーナーさんたちが言っていることと、会社が言っていることって、やっぱりぜんぜん違います。会社からいわれることといえば、営業利益とか四半期の決算とか、そんな話ばかりでした。上場企業だったので、当たり前なんですけどね。
一方でオーナーさんたちは、小さくても自分の城をもって、そこで自分なりの哲学や表現を貫いていて。「自分がやりたいのはこっちなんじゃないか」という思いが、どんどん大きくなっていきました。
いくら会社として立派なスローガンを掲げていても、実際にやっているのは銭勘定ばかり。それになんの意味があるんだろう? そう考えると急に、会社から与えられる数字をクリアすることが、どうでもいいことのように思えてしまったんです。
当時、営業所長に昇進する話もあったのですが、それも断って退職しようと思いました。でも、会社から引き止められて。いったんは異動して、新規事業の立ち上げをやることになりました。それから2年ほど経って、事業も軌道にのりはじめたタイミングで、改めて会社を辞めたんです。27、8歳のときでした。
邪道で勝つ
ぼくはビルゲイツやスティーブ・ジョブズのように、すごい才能をもって世界にイノベーションを起こせるような人間ではありません。平凡でなんにもない。そんな自分なりの勝ち方を、ずっと探してきたような気がします。誰も行かないような方向に、あえて歩み寄っていく。
最終的にそれがうまくいったのが、弁才天だったんです。
ふつう、和菓子職人の方がフルーツ大福をつくると、どうしても力の入れどころが餅とあんになってしまいます。でもぼく、じつは甘いあんこがあまり好きではなくて。そこで弁才天では「フルーツが主役」のフルーツ大福を目指しました。薄い牛皮に、薄い白あん。旬のフルーツをいちばん味わえるバランスにしています。
店舗やホームページのデザインにもとことんこだわっています。弁才天の店舗は、ひとつひとつ内装のコンセプトがちがうんです。たった4坪の店舗に、1500万円も内装費をかけていたりもします。ふつうのロジックでは考えられない費用です。
でも、ぼくは単なるブームではなく「カルチャー」をつくりたかった。
大福そのものはもちろん、行列に並んでいるあいだも、店舗の雰囲気も、糸で大福を切るという所作も、すべてにワクワクしてほしかったんです。そのために必要な投資は、まったく惜しみませんでした。
やっぱり、反骨精神とかひねくれ根性みたいなものが、中小企業を勝たせるんだと思います。誰もが考えつくようなことをしていたら、資本の論理からは抜け出せません。結局、お金をたくさん持っているところが勝ってしまう。でもアイディアがあれば、その土俵から抜け出せるんです。
弁才天の成功には再現性がある
弁才天をはじめてから3年が経ちました。
いま冷静に分析すると、この成功には再現性があると思っています。要は「視点のずらし方」だと思うんです。和菓子業界という旧態依然たるもの、変わろうとしないものがあって、そこに新しい切り口を持ち込む。弁才天の場合は、それが「デザイン」だったわけです。
和菓子業界という場所では「デザイン性」という風が浸透していなかった。そこにたまたま目をつけたから成功した。……だとしたら、これは再現性がありますよね。旧態依然たる業界や組織は、ほかにもいっぱいあるわけですから。
それはガソリンスタンドかもしれないし、薬局かもしれない。最近はいろんなものが洗練されていっているので、見つけるのは難しくなっているかもしれません。でも、かならずあるはずです。そこに対して同じアプローチをすればいい。
表現力をもって古い業界にイノベーションを起こしていく。この手法は応用がきくんです。
ファンドに株を売却した理由
この成功には再現性がある。じゃあ、ぼくはどうしたいのか? それをもう一回、二回、三回とくり返して、そのたびに会社を売って、お金を増やして……。べつに、そういうことがしたいわけではないんです。
今年から、弁才天はファンドに資本参加してもらうことにしました。
いちばんの理由は、ぼくの管理業務が増えすぎたこと。弁才天はいま70店舗になっています。規模が大きくなればなるほど、日々の業務に忙殺されて、クリエイションやおもしろい企画を考える時間が削られていくことに、焦燥感があったんです。
採用して組織を大きくすることも考えましたが、それは自分にはあまり向いていない気がして。「弁才天らしさ」は守りつつ、管理部門だけを外注させてもらうような形で、ファンドに入ってもらったんです。おかげでずいぶん楽になって、クリエイションにきちんと時間をさけるようになりました。
けっきょく「ビジネスマン」の自分がダサい
採用して組織をつくるのではなく、ファンドを入れる。垂直に拡大するのではなく、フランチャイズで水平に増やす。こういう手法はある意味「上手い」のだと思います。その点で、ぼくはやっぱり「ビジネスマン」なんです。アーティストや職人のほうにふりきれているわけじゃない。
そんな自分がなんだか偽物のように思えて、イヤになるときもあります。
ほんとうにかっこいいものって、規模を追求していない気がするんです。SIMPLICITY(シンプリシティ)の緒方さんがやられている、青山の「HIGASHIYA」やフランスの「OGATA」みたいに、多店舗展開せずひっそりと、見せ方も食材もこだわり抜いたすばらしいものを提供する。
そういう人と比べると、自分が「コマーシャニズムの権化」みたいになっているような気もしてしまうんです。彼らのほうが本質なんじゃないか? フランチャイズで水平展開して店舗を増やしている、この行為自体がもうダサいんじゃないか? と。
でも、ぼくにはこのやり方しかわからなかった。フランチャイズとなると、店舗ごとにプレイヤーも変わります。ぼくがやりたいことを100%実現できるわけではもちろんなくて。思い通りにならないこともたくさんあります。
一方で、ぼく以上に現場と関わって、いいお店をつくっているオーナーさんもたくさんいます。そういう方たちを見ると「ああ、よかったな、この広げ方で」とも思うんです。それに、規模を広げなかったらできなかった経験や、出会えなかった人もたくさんいます。
難しいです。ずっとその葛藤はあります。
いっそカラフルな古墳でも造ろうか
これからどうしていこうか、いまはいろいろ考えているところです。また自分でゼロから新しいことをやろうかな、とも思います。
ただ、そもそも「ビジネス」がやりたいのか? というところから悩んでいて。
アメリカの西海岸に「サルベーションマウンテン」という山があります。ヒッピーのおじいさんが一生かけて作った、ピンク色のド派手な山です。砂漠の真ん中に、ド派手なでかい山がとつぜん現れる。それがいまはランドマークみたいになって、みんな何時間もかけて砂漠を移動して、おじいさんのつくった山を見にきているんです。
砂漠のど真ん中に山をつくる。それってビジネスの論理からすると、頭がおかしい行為です。ビジネスではふつう、投資と回収がセット。でもこの山は投資&投資です。つくったおじいさんはもう亡くなっています。そもそも回収なんて微塵も考えていない。つくりたいからつくったわけです。
実際に見に行ったことがあるのですが、静かな風が吹いていて、すごく気持ちのいい場所でした。
ぼくはなんだか涙が出たんです。じいさんが一人でこれをつくって、亡くなった後もみんながこの場所を訪れている。「偉業ってこういうことなんだ」と思いました。
ぼくは、投資で億万長者になったウォーレン・バフェットのことを、べつに尊敬していません。すごいな、上手だなとは思うんですけど、尊敬はしていない。ぼくが尊敬する人を思い返してみると、誰のことも「お金持ちだからすごい」なんて思わないんです。ジョン・レノンやチェ・ゲバラ、カートコバーン、マザーテレサ、宮沢賢治みたいな人たちのことを、ぼくは心から尊敬しています。
じゃあ、自分もそこを目指さなきゃいけないんじゃないか。ビジネスでちまちま投資回収をやっていても仕方がない。株を売って資産運用して、億万長者になってる場合じゃないですよね。
ぼくもいっそ、自分の墓でもつくろうかなあって思います。古墳でもつくろうかな。カラフルな古墳。
でもこんなふうにカッコつけて話しているわりに、ほんとうに「自分の満足」のためだけになにかをつくるのはイヤだなあとも思うんです。ゴーギャンみたいに、死後に評価されてもなあ。せっかくやるなら、なにかしら人や社会の役に立つほうがいいなあ、って。
ポリシーも評価も両方ほしい。わがままなんですよね。
オンリーワンかつ、ナンバーワンになれる場所を探してきた
なにかに似てたらダメだ。なにかと比較されたら勝てない。そんな習性が、小学校のころの経験から身についているのかもしれません。オンリーワンにならなきゃいけない。しかも、ただオンリーワンなだけじゃダメで、ちゃんとマーケットがないと成功しないんです。
オンリーワンかつ、ナンバーワン。そうなれるところを探して、ぼくはここまできたんだと思います。
多くのロックスターたちは「ロックの矛盾」に苦しみます。彼らは下手したらスラムみたいなところから音楽で這い上がって、権力や権威に対するアンチテーゼとして、ロックを奏でてきたわけです。
権威に対抗する側だった彼らが、売れてしまったら今度は自分たちが「権威」の側にいくことになる。それでカートコバーンなんかは、おかしくなって自殺してしまいました。
そうやって儚く、美しく散っていくスターにはやっぱり憧れます。なかなかそんなふうにはなれないけれど、ぼくもつまらない小金持ちにはならないように、気をつけなきゃなと思います。
「わかる人にだけわかればいい」と完全に閉じるわけでもなく、かといって大衆に迎合するわけでもない。「外れもの」のまま、インディーズ感があるままでメジャーになるのがカッコいいと思うんです。
かつてのぼくへ
なにもない自分がコンプレックスだった幼少期。尖りすぎて社会不適合者といわれた20代。なんだか「自分らしさ」というものに振り回された半生でした。
最近は、ようやく「自分らしくやってりゃいいんだよな」と思えるようになりました。それぐらいの成果が伴ってきたからです。むしろ自分らしさを貫くことが強みになった。「これが僕のスタイルなので」と、堂々と言えるようになりました。
ぼくの言っていることって、大学生ぐらいからそんなに変わっていないんです。大学のみんなでコンパをしたときも、ぼくは女の子にチェ・ゲバラやジョン・レノンの話をしていました。そのときは当然「めんどくせえやつだな」と思われて終わりです。
でもいまは、ぼくがくだらないことを話しても、みんな耳を傾けてふむふむと聞いてくれます。ぼく自身はなんにも変わっていないけど、立場が変わったら周りのみんなが変わったんです。それがいいとか悪いとかじゃなくて、人間ってそういうものなんだと思います。
逆に15年前のぼくには、まだそれを話す資格がなかったということです。いまはようやく、語ってもいい権利を与えてもらえたのかなと。
あのころのぼくにもし会えるなら、「大丈夫だから、そのまま自分らしくがんばれよ」って、背中を押してあげたいなって思います。